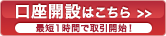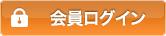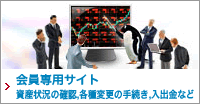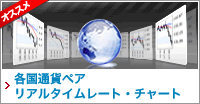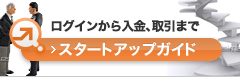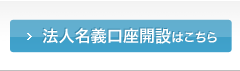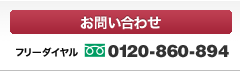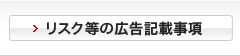2025年1月28日、スコット・ベッセント氏(Scott Bessent, 62)が、米79代財務長官に正式に就任した。トランプ政権発足から9日目、既に大統領令で政策発動がされているが、政権の中でも重要な閣僚が正式に始動することになったことで、これからはよりダイナミックな変化が起きると新財務長官の言動に耳目を傾けたい。ちなみに財務長官は、大統領の継承順序で5番目(1番目は副大統領で、次いで下院議長、上院仮議長、国務長官)という高位である。
ベッセント財務長官は通貨と債券のスペシャリストであり、一時期為替市場に向かっていたことが米財務省のプレスリリースで判明した。まさにポリティカルエコノミーの体現者あるいは仕掛け人であると言え、筆者は少なからず縁を感じている。
まず、ポリティカルエコノミーについて触れたい。筆者が為替相場見通しを考える時にベースにしている言葉だ。53年にわたる為替市場への関わりにおいて、幾度となくこの言葉に当てはまる経験に遭遇していることで、為替相場は最終的には政治が決定するとの考え方に至っている。その経験を紐解くと、最初は1978年のカーターショックであった。筆者はニューヨーク支店で為替ディーラーだったが、一日で180円~200円の約20円の乱高下を経験した。行き過ぎたドル安を反転させるためにカーター米大統領の決断で、米国が外貨(当時はドイツマルク債、スイスフラン債)を発行し、米国政府が発行替わり金をその通貨売り/ドル買いでドル高をもたらすという政策であり、ドルが急騰した。
1985年のプラザ合意も、米国政府が仕掛けた為替政策と言う点で同じ流れである。プラザ合意は、ベーカー財務長官(当時)が主導し、行き過ぎたドル高を反転させるために主要5か国(G5)がNYのプラザホテルに秘密裏に集合して、ドル売り協調介入を決めたことだ。ドル円は250円から200円割れとなった。
そして筆者にとって一番の大きな転機は、1988年に、当時ヘッジファンドの神様と言われたジョージソロス氏に会ったことだった。1992年にBOE(バンク・オブ・イングランド、英国中央銀行)を相手にポンド売りを仕掛け、一晩で10億ドルの利益を上げて一躍有名になったそのソロス氏である。出会いはその4年前であるが、G7首脳会議の帰国直後の米財務次官との少人数会合に同席した時だ。この会合により「為替相場の最終決定者は政治である」と認識して、それ以降ポリティカルエコノミーに深く関わってきた。
なんと、ベッセント財務長官が、1991年から2000年までソロスファンドのロンドンオフィスのマネージング・パートナーであったことが分かった。まさに為替相場を動かした張本人であり、今度は国家レベルでドル相場の命運を握ることになる。トランプ大統領のドル相場の考えを忠実に実行するとともに、自身の考え方を具現することもできる立場となる。しっかりフォローしていきたい。
さて、市場は毎日動いている。マクロで俯瞰することで歴史的な軸を確認することは重要であるが、足元では毎日、毎時動いている。今日は世界の金融界のリーダーであるFRBのFOMCが金融政策を決定する日だ。シカゴ先物取引所(CME、シカゴ マーカンタイル エクスチェンジ)で発表されているフェドウォッチ(金融取引をベースに、FOMCで決定される政策金利予想値の確率)では、99.5%の確率で「据え置き」となっている。
そこで、今後1週間の相場予想であるが、日銀が利上げしたが、日米金利差だけで論じれば現時点では大きな変化をもたらさないことから、154.00-157.00円とドル強含みと予想。またユーロドルは、今週はECB利下げ予想を背景に1.0250-1.0550とユーロ安を、ユーロ円は160.50-163.70円と予想する。そして英ポンドドルは1.2250-1.2550のポンド強含みを予想する。
(2025/1/29、 小池正一郎)
FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-